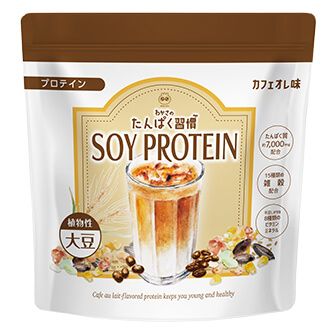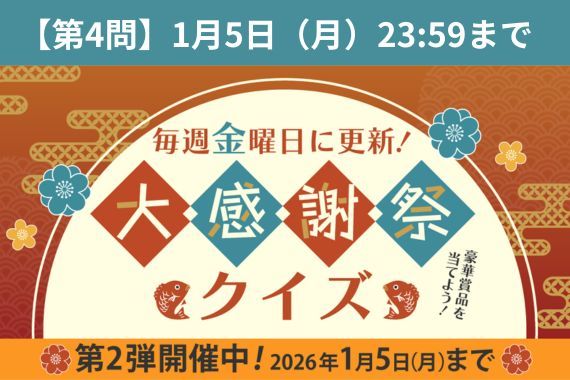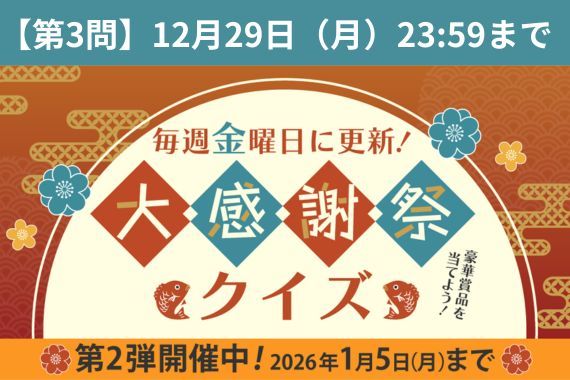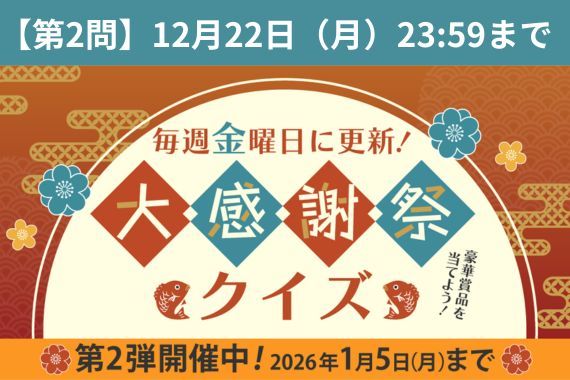わかさのOshi-log(おしログ)
フィンランド式サウナの歴史と暮らしとの関わり

森と湖の国フィンランド。
そこでは古代からサウナが暮らしに溶け込み、家族や友人の語らい、さらには人生の節目を見守ってきました。
サウナという言葉は世界的に知られていますが、その背景をたどるとフィンランド人の価値観や精神性が垣間見えてきます。
本記事では、そんなサウナがいつ生まれ、どう暮らしに溶け込んできたのかをご紹介します。
サウナの起源

歴史には諸説ありますが、世界最古のサウナは石器時代ごろに作られたと考えられています。
その仕組みは、地面の斜面に穴を掘り、燃やした薪で石を熱し、そこに水をかけ蒸気を発生させるというもの。
今も伝わるサウナのは形は、このときから存在していたのです。
その後サウナは、分娩や遺体の清めにも使われるなど、フィンランドに住む人々にとって欠かせないものになっていきました。
神聖なサウナ
森と湖の国フィンランドでは、サウナは教会のように静けさを守る"家の聖域"とされてきました。
石に水を打つロウリュは蒸気であり魂を再生させる霊気と考えられ、入浴前にそっと祈りを捧げる習わしがあります。
小さな守護精霊サウナトントゥは火を見張り、サウナで騒ぐ人には怒りを示すと伝えられました。
また、熱い蒸気で病を癒やす女神サネルヴァタルや浄化をもたらすアウテレタルなど、神々は誕生から看取りまで人生の節目をサウナで見守ってきたとも語られています。
現代に残るサウナの習慣の随所に、こうした神話の温もりが息づいているのです。
誰しもが平等に扱われるサウナ

フィンランドにおいて、サウナは誰もが平等に、敬意をもって扱われる場だとされています。
身ひとつで入るサウナでは地位も肩書きも意味を為さないため、ある種で絆や議論を深める手段としても使われるのだとか。
実際、フィンランド政府のパンフレットには「多くの重要な決定はサウナで行われる」と書かれているほどなんですよ。
ことわざが語るサウナ愛
「サウナ、ウイスキー、タールでも効果がなければ、この病気は致命的である」
「サウナは貧乏人の薬局」
こんなことわざまであるほど、フィンランドでサウナは万能薬扱い!
実際に2023年に行われた研究では、週3回以上のサウナは高血圧による心血管疾患のリスクを相殺するという結果も出ています。[1]
古代から脈々と受け継がれてきたサウナの魅力は徐々に世界へと広まり、2020年にはユネスコの無形文化遺産に登録されました。[1]
フィンランド式サウナの楽しみ方
「熱い箱に入って汗をかくだけ」と思われがちなサウナ。
しかし、本場フィンランドでは温度・湿度のバランスや外気浴のタイミングにまで"黄金ルール"があり、慣れた人ほど細やかにこだわります。
ロウリュで蒸気をつくり、湖へザブンと飛び込んでクールダウン。
そんな一連の流れがあるからこそ、体も心も整うのです。
ここでは作法やマナーなど、今日から試したくなるサウナの楽しみ方をまとめました。
ロウリュの作法

サウナストーブに水をかけて蒸気を立ち上げる行為を「ロウリュ」と呼びます。
かける前には「ロウリュいいですか?」と周囲へひと言かけるのが暗黙のマナーです。
また、一度に大量の水をかけると湿度が上がり過ぎてしまうので注意しましょう。
湯気が立った瞬間に深呼吸すると、皮膚だけでなく気道もじんわり温まり、発汗が一段とスムーズに。

さらに、白樺の枝を束ねたヴィヒタで軽く肌を叩くと血行が促進され、天然木のアロマティックな香りがリラックスを後押しします。[2]
温度・湿度・冷水浴の黄金バランス
伝統的なフィンランドサウナの室温はおおむね70〜90℃、湿度は高めが王道です。[1]
熱気でしっかり汗をかいたら、テラスや湖畔で外気浴を数分。
体の温度がほどよく下がったところで再びサウナへ。
これを2〜3セット繰り返すと、自律神経が整い、深い睡眠をサポートすると言われています。
本場のマナーと日本式との違い
フィンランドでは「裸が基本、男女は別室」が一般的。
ただし混浴の場合は必ず水着やタオルを着用します。[1]
公共のサウナにはタオルが用意されているので、板を汗で濡らさないために敷くと良いでしょう。
またフィンランドのサウナでは静かに過ごしたい人が多いので、会話は控えるのがベターです。
まとめ|フィンランド式サウナで"ととのう"毎日を
フィンランド式サウナは神聖でありながら身近なものとして、今も暮らしに寄り添い続けています。
本場ならではのロウリュや外気浴、白樺の枝葉「ヴィヒタ」の香りが生む深いリラックス感は、今や世界中を虜にしてやみません。
お疲れ気味の現代人にとって、サウナを使った温冷交代浴は血行促進や冷え対策、睡眠の質向上に役立つ頼もしい味方。
蒸気と冷気が奏でる爽快なリズムを日常に取り入れて、毎日をもっと心地よくととのえましょう。
 わかさのOshi-logトップページへ >
わかさのOshi-logトップページへ >