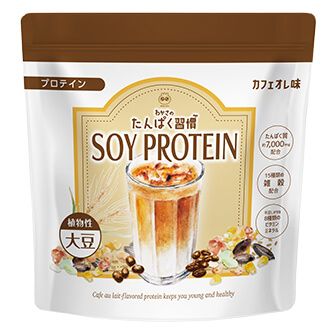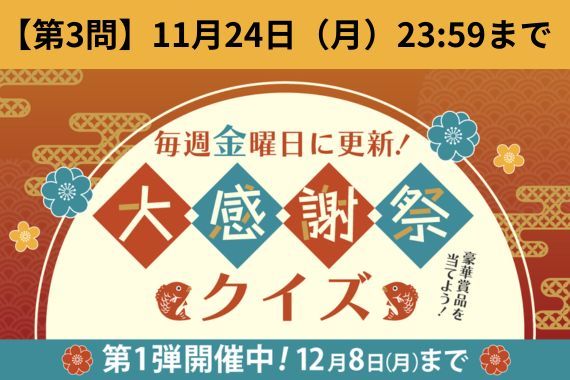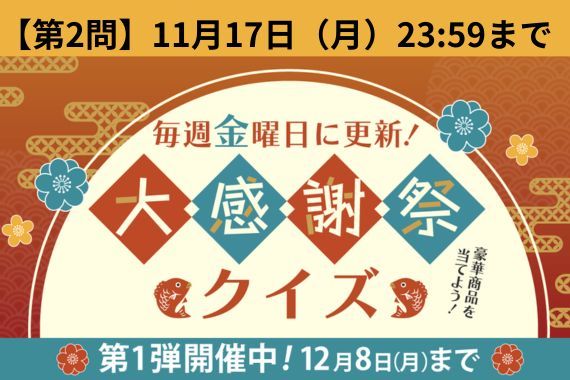わかさのOshi-log(おしログ)
おなかの温活で寒い季節も元気に過ごそう!冷えの原因や方法をご紹介

寒い時期になるとおなかが冷たくなる方はいませんか?
おなかの冷えは、おなかの不調にとどまらず、食欲や免疫の低下につながります。
寒い時期はどうしても体が冷えやすいので、毎日のルーティンに体を温める習慣、温活を取り入れておなかの冷えを予防することが大切です。
本コラムでは、おなかが冷える原因や冷えのリスクとおなかを温める重要性、実践しやすい温活方法をご紹介します。
おなかの冷えが気になっている方、すでに冷えからくる不調に悩まされている方は、ぜひ参考にしてください。
おなかの冷えチェック

まず、おなかが冷えているかをチェックしてみましょう。
以下の症状は、おなかが冷えているときにみられます。
● おなかを触ると冷たい
● おなかの不調を感じやすい
●食欲の低下を感じる
●風邪をひきやすい
●トイレが近い
当てはまる数が多いほど、おなかが冷えている可能性があります。
冷えの原因を取り除き、温活を取り入れておなかを温めましょう!
おなかが冷える原因

おなかが冷える原因には以下があります。
●運動不足
●冷たい食べ物・飲み物の摂りすぎ
●からだを冷やす食材の摂りすぎ
●ストレスや疲れの蓄積
運動不足
外運動不足は血流が悪くなり、冷えの原因です。
普段座っていることが多い方は、意識的にからだを動かしてみましょう。
冷たい食べ物・飲み物の摂りすぎ
冷たい食べ物や飲み物の摂りすぎは、おなかを冷やしてしまいます。
アイスやかき氷などの冷たい食べ物は、食べる量に気を付けましょう。
飲み物は常温や温かいものを飲む習慣をつけ、冷やさないように意識することが大切です。
からだを冷やす食材の摂りすぎ
トマトやなす、きゅうりなど、夏野菜にはからだを冷やす作用があります。
夏にはぴったりですが、寒い季節はできるかぎりからだを温める作用のある食材を選びましょう。
ストレスや疲れの蓄積
ストレスや疲れが蓄積すると自律神経のバランスが崩れます。
自律神経の乱れは血流を悪くさせるため、おなかの冷えにつながります。
参考資料:
・冷え性 -生活改善や漢方薬が効果的-
・内臓冷え ~新しい生活様式~
おなかの冷えは体の不調につながる!温めることが大切
おなかが冷えると、体のあらゆるところで不調を感じるようになります。
まず、おなかが冷えると胃腸の機能が低下します。
便のつまり、便が柔らかい、おなかの痛み、食欲が落ちるといった不調が見られます。
また、冷えによる胃腸機能の低下は、免疫力が低下するといわれているため注意が必要です。
ある論文の発表で、冷えたおなかなどを湯たんぽで温めることで、リンパ球の数が増加することがわかりました。
健やかでいるためにも、おなかを冷やさないことが大切です。
次におなかの温活方法をご紹介しますので、ぜひ参考にして実践しましょう。
参考資料:
・Biomedical Research
・腸と免疫
・冷え性 -生活改善や漢方薬が効果的-
・体に悪影響を及ぼす「冷え性」を改善
おなかの温活方法を3つご紹介!実践してみよう

ここでは、おなかの温活方法を3つご紹介します。
温活方法には、外側からアプローチする方法と内側からアプローチする方法があります。 すぐに実践できる方法もご紹介していますので、ぜひできることから実践してみましょう。
外側から温める
外側から温める方法に、グッズを使用する方法があります。おすすめは、腹巻・カイロ・湯たんぽです。
- 1.腹巻の選び方
- 腹巻に使われる素材にはたくさんの種類があります。 しっかりと温めたい方は、温泉成分やトウガラシ成分などが加工された温熱素材の商品がおすすめです。 通気性が気になる方はコットン素材、肌ざわりが気になる方はシルク素材の商品もあります。
- 2.カイロの選び方
- カイロには、使い捨てタイプや充電式タイプのカイロがあります。 使い勝手を考えると、貼り付けられるタイプがおすすめです。 充電式のカイロは腹部に貼り付けられないため、おなかの温活には向いていません。
- 3.湯たんぽの選び方
- 湯たんぽには、腹巻になっているタイプと昔ながらの容器型タイプがあります。 湯たんぽを使用される方は、おなか用の湯たんぽを探しましょう。 なかでも、姿勢の制限なく使いたい場合は腹巻タイプの湯たんぽがおすすめです。
内側から温める
- 1.温かい飲み物を摂る
- 温かいドリンクやスープを飲むと、からだの内側から温められるので、寒い季節の温活にピッタリ!
手軽に取り入れられるのが白湯を飲む習慣です。
白湯のみだと飲みにくい方は、レモンやはちみつ、しょうがなどを入れると飲みやすくなります。 - 2.スパイスを摂る
- スパイスには体を温める作用があります。
特におすすめなのが、しょうがやシナモンです。
しょうがやシナモンを使ったレシピがたくさんあり、取り入れやすいためです。- <しょうがのおすすめの取り入れ方>
しょうがは、「白湯」や「ノンカフェインティー」「スープ」など、温かい飲み物に入れるのがおすすめです。 相乗効果が期待でき、おなかを含め体全体をしっかり温められます。
- <シナモンのおすすめの取り入れ方>
シナモンはりんごとの相性が抜群。 「アップルシナモン」や「アップルパイ」などのスイーツにシナモンを入れるとおいしく召し上がれます。
- <しょうがのおすすめの取り入れ方>
フランスのホットワイン「ヴァンショー」もおすすめです。 冬が長く寒いフランスで、昔から飲まれているスパイスが入ったホットワインです。
まとめ|グッズや食事でおなかの温活をしよう
おなかが冷えると、おなかの不調や風邪をひきやすくなるといった不調を招きます。 日頃から冷やさないように、おなかを温めることを意識することが大切です。 温活方法には、腹巻などのグッズを使用する方法や温かい飲み物の摂取、スパイスを取り入れる方法があります。 おなかを触って冷たく感じたり、おなかの不調を感じることが多かったりする方は、おなかの温活を始めてみませんか?
関連商品

IFMC.温泉腹巻き
身に着けるだけのお手軽温活グッズ
3,500円

IFMC.温泉レギンス
履くだけ温活グッズ
3,500円

IFMC.温泉レッグウォーマー
足元からあたたか温活グッズ
4,500円
 わかさのOshi-logトップページへ >
わかさのOshi-logトップページへ >